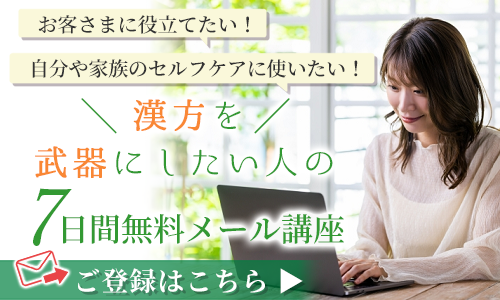春らしい暖かな気温になると、くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、肌あれなど、不快な症状が出る花粉症の人が増えます。
今年の春は、風が強い日が多く、かなり花粉が飛んでいるのかもしれません。
今年は、花粉症の症状が辛いというお声をよく耳にします。
体質改善で薬が不要になった私も、今年はホコリや花粉でコンタクトレンズがゴロゴロします!

毎年、花粉症のこの時期になると、こんな質問をよく頂きます。
花粉症で「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」という漢方薬を何年も前から耳鼻科で処方してもらい、ずっと服用しています。
毎年、服用している時は症状が緩和しているけど、今年も花粉症の症状がまた出てきました。
よく漢方薬は体質改善と聞きますが、本当に漢方薬の治療で、花粉症が治るのですか?

漢方薬の全てが体質改善ではありません!
まず、上記にの質問に対してキッパリお答えします!
漢方薬の治療を含め、漢方を武器にして体質改善すれば、花粉症は治ります。
私がその経験者のひとりだし、私の多くのお客さまも花粉症が改善しています。
ここで1つ大切なポイントです!
花粉症だけでなく、もし、あなたが今、医師から処方されて漢方薬を服用している場合、どんな目的でどのように体に働きかける漢方薬なのかを知って服用することが大切です。
それというのは、漢方薬の全てが体質改善や根本治療が出来ると思っている方が多いからです!
でも、それは間違いです。
漢方には、対症療法の標治(ひょうち)と体質改善の本治(ほんち)の2種類があります。
▼詳しくは、下記の記事をお読みください。
漢方薬にも、この両方があります。
つまり、西洋薬と同じように出ている症状をただ抑える(緩和する)ためだけの標治の漢方薬と体質改善をバックアップしてくれる本治の漢方薬があります。
花粉症の時によく処方される小青竜湯は、この標治のための漢方薬です。
体内の水分の巡りが悪く、余分な水分を体内に溜め込むことにより、花粉やホコリという刺激によりくしゃみを連発したり、水っぽい鼻水の症状が出るタイプの花粉症に使います。
体を温めて水分代謝を助けることで、体内の要らない水分が尿や汗で排泄され、花粉症の辛い症状を緩和する漢方薬です。
そのため、小青竜湯をいくら長く飲み続けても、体質改善はできません。
しかも、水っぽい鼻水ではなく、鼻づまりが強い花粉症のタイプの人には、この漢方薬では症状を緩和できません!

では、なぜ標治の漢方薬を使うのでしょうか?
それは、症状が出ている時は、症状を緩和しないと、生活の質「QOL(Quality of Life)」を保てないからです。
最近の抗アレルギー薬は、「眠くなる」「のどが渇く」「便秘になる」「鼻の中が乾燥して痛い」などの副作用は、だいぶ軽減されています。
しかし、体質的に西洋薬で副作用が出やすい方や抗アレルギー薬は、胎児の奇形性が高いものが多く、妊婦の方は飲めないからです。
ただし、標治の漢方薬で生活のQOLが保てるからと、漢方薬に依存し過ぎるのは危険です。
漢方薬も薬ですから、強い作用の成分が含まれる漢方薬は、長く服用すれば、副作用が出やすくなります。
この小青竜湯も、「麻黄(マオウ)」という強い作用の成分が含まれています。
そのため、人によっては、その成分が胃腸に負担をかけて胃腸障害を起こす方がいます。
私のお客さまでも、アレルギー性鼻炎のために耳鼻科で処方されていた小青竜湯を一年中服用したことで、胃の調子が悪くなった方がいました。

症状が落ち着いている時に体質改善を!
そこで、標治の漢方薬をずっと服用しないためにも、症状が落ち着いてきたら体質改善に取り組むことが重要です。
特に、今、花粉症の症状が辛くて、抗アレルギーを服用されている若い女性は、体質改善をおすすめします。
なぜかというと、妊娠したら胎児の奇形性の関係で、抗アレルギー薬を服用できないからです。
花粉症で体質改善するには
- なぜ不要なものを溜め込んでいるのか
- なぜ冷えてしまうのか
- なぜ余分な熱がこもってしまっているのか
- なぜバリア機能が弱っているのか、など
その人の体質を読み解いて、根本原因をしっかり見きわめる必要があります。
不調や病気は、下記のA + B の体の状態が現れています。
生まれつきの体質 →A
後天的に体内のバランスの乱れを作り出した食事を含めた生活クセやその人の思考クセ →B
簡単に言うとBの部分は、無意識からやってしまっている生活習慣や思考のクセ
このBの部分を改善することが漢方では、体質改善になります。
生まれつき花粉症だったわけではないですよね!
花粉症は、体内に不要なものを溜め込んでいることを知らせるサインのことが多いです。
体内に不要なものを溜め込んだ時に起こる不調や病気について、下記で詳しく書いているので参考にしてください。
【関連記事】
そこで、漢方を武器にして体を診て行けば今の体の状態という現在地がわります。
現在地がわかれば、快適という目的地への道筋が見えて生活の見直しポイントがハッキリとわかります。
これが漢方を武器した体質改善です。
今、何か辛い症状がある方は、まずは、ご自分の現在地を知ることが第一歩です。
あなたが漢方薬を服用されている場合、その漢方薬がどんな目的で、どのように体に働いているか知っていますか?
それを知って服用することで、体質改善の効果が違ってきます。
だから、あなたに分かりやすい言葉でそれを知るお手伝いも個人セッションでしています。
ぜひ、体質診断の個人セッションをご活用ください。
このような考え方をする漢方をあなたも、武器にしたいと思いませんか!
しかし、漢方を一度学んだけど、上手く使えないというお話をよく聞きます。
それは、漢方を使いこなすための「ある方法」を知らないからです。
漢方薬局で、のべ500人を超える患者さんを治療してきて、独立後1000名以上のお客様をサポートしている薬剤師で国際中医師の藤巻祥乃が発見したその秘密を下記でおしえています。
漢方を使いこなしたい方は、ぜひ下記から読んでください。